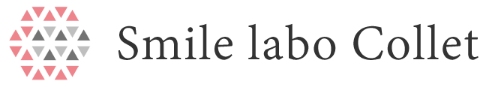自分軸で生きる人は、なぜ疲れにくいのか
2025年05月21日

Contents
「ちゃんとしなきゃ」が口癖のあなたへ
日々、家庭のこと、子どものこと、職場でのチームマネジメント……
やるべきことに追われながら、「ちゃんとしなきゃ」と自分にムチを打っていませんか?
東京都内で働く42歳の女性会社員Aさんも、
同じように「責任ある立場で頼られながらも、心はずっと疲れている」と悩んでいました。
「夫に不満があるのに言えない」
「家では小言ばかり」
「子どもに優しくできない自分が嫌い」――
こんな思いを抱える女性たちは、実は「他人軸」で生きている状態かもしれません。
では、「自分軸」で生きる人は、なぜ疲れにくいのでしょうか?
その理由を、脳科学と心理学の観点から紐解きます。
1. 「他人軸」は脳にとって負荷が大きい
他人の評価を基準に行動する「他人軸」で生きていると、
常に外の世界に気を張らなければなりません。
・夫にどう思われているか
・ママ友に嫌われないか
・部下に頼られているか
このように、他人の目を気にする状態では、脳の「扁桃体」が過敏になり、
ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されやすくなります。
これが、慢性的な疲れや不安、怒りやすさの原因となるのです。
2. 自分軸は「選ぶ基準」が自分の内側にある
一方で、自分軸とは「自分の価値観・感情・望み」を基準に選択する生き方です。
誰かのためではなく、「私はどうしたいのか?」を問い続けることで、
無駄な気疲れや罪悪感が激減します。
たとえば、
・「夕食は完璧じゃなくてもいい。今日はお惣菜にしよう」
・「子どもにイライラしてしまったけど、まずは自分を休ませよう」
こうした小さな選択の積み重ねが、自分との信頼関係を強め、
結果的に“回復力の高い脳”を育てるのです。
3. 無意識が整うと「自分を責める回路」が緩む
自分軸で生きる人は、無意識レベルで「自己否定」を手放しています。
「また文句言っちゃった…」
「こんな自分じゃダメだよね…」
このような自己批判がクセになっていると、脳はその言葉を現実として受け取ってしまいます。
でも、自分軸で生きる人は、自分に対しても「寄り添う言葉」がけをするようになります。
これは、脳の前頭前野が活性化し、冷静な判断力や共感力が育つ状態。
つまり、感情の起伏が穏やかになり、「怒らない」「疲れない」心のベースが整ってくるのです。
4. 周りとの関係も自然とラクになる
興味深いのは、自分軸で生きるようになると、
他人との関係も良好になるということ。
・夫に「もっと○○してよ!」と言う代わりに、
自分の気持ちを素直に伝えられる
・子どもに怒りをぶつける前に、「ママも疲れてるんだ」と伝えられる
・職場でも、必要以上に抱え込まず、適切に手放せるようになる
自分が整うことで、相手にも優しさや余裕を持てるようになるのです。
5. 「自分軸」は特別な才能ではない
ここまで読んで、「でも私には無理…」と思った方もいるかもしれません。
でも安心してください。自分軸は、誰にでも育てられる“後天的な習慣”です。
まずは、自分の感情に「気づくこと」から始めてみましょう。
「今、私は疲れてる」
「本当は、誰かに頼りたい」
「ちょっとイライラしてるな」
そんな風に、心の声に耳を傾けてあげるだけで、
自分軸は芽を出し始めます。
そして、無意識を整えるセッションやワークを通じて、
その軸はどんどん太く、強くなっていくのです。
最後に:疲れにくい人生は「自分を大切にする」ことから
「他人の期待に応えなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」――そんな思いが強いあなたへ。
今こそ、自分の声に耳を澄ませてみてください。
「私はどうしたい?」と問いかけてあげてください。
疲れにくい人生のカギは、外ではなく、あなたの中にあります。
無意識を整え、自分軸で生きることで、もっと軽やかに、
もっと自分らしく毎日を楽しめるようになりますよ。