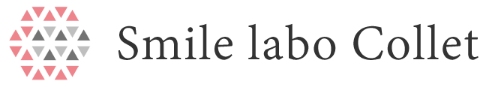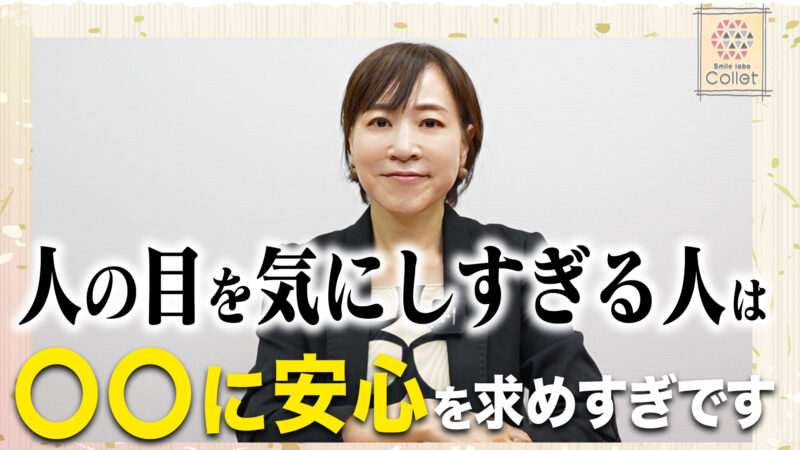アダルトチルドレンが「自分軸」を見失う理由と回復の第一歩

Contents
アダルトチルドレンが「自分軸」を見失う理由と回復の第一歩
はじめに
「自分軸で生きたいのに、気づけば他人の顔色ばかり見てしまう」
「本当はこうしたいのに、
“怒られたくない”“嫌われたくない”が先に立つ」
──そんなふうに感じることはありませんか?
それは性格の問題ではなく、
幼少期の家庭環境(機能不全家族)の影響で身についた
“生き延びるための癖”かもしれません。
こうした背景を持つ人はアダルトチルドレンと呼ばれます。
アダルトチルドレンとは?
アダルトチルドレン(Adult Children)とは、
子どもの頃に家庭内で心の安心が得られない環境──
たとえばアルコール依存症、暴力、過干渉、ネグレクト(育児放棄)などの中で育ち、
「本当の自分」を抑えて生きざるを得なかった大人のこと。
成長後も、
- 人間関係がぎこちない/距離感が分からない
- 依存や共依存の関係を繰り返す
- 自己肯定感が低く、自信が持てない
といった「心の不調」を抱えやすくなります。
なぜ「自分軸」を見失ってしまうのか
機能不全家族では、「親の機嫌」や「家庭の空気」に合わせて行動することが生き残りの術でした。
例えば、
- アルコール依存症の親の怒りを避けるため、いつも空気を読む
- 母親がうつ病で不安定なため、子どもが世話役(ケアテイカー)を担う
- 兄弟の中で問題児(スケープゴート)として扱われ、責められる
こうした環境では、「自分の気持ちを感じる」より「親をなだめる・怒らせない」が優先されます。
その結果、「私は何を感じている?」「本当は何をしたい?」が分からなくなり、
自分軸を失うのです。
「他人軸」で生きることの苦しみ
自分軸を失うと、他人の反応が常に気になり、
批判を恐れて無意識に自己否定を繰り返します。
「嫌われたくない」
「うまく振る舞わなきゃ」
「我慢すれば分かってもらえる」
──こうした“他人軸”の生き方は、表面上は優しく献身的に見えても、
心の奥では怒り・悲しみ・孤独感が溜まり、
やがて不安障害やパニック障害、抑うつ状態として表れることもあります。
回復の第一歩は「無意識のパターン」に気づくこと
アダルトチルドレンの回復に必要なのは、まず自分の無意識を知ること。
行動や思考の多くは無意識に動かされています。
カウンセリングや心理療法では、「自分を責める」癖の奥にあるメッセージを見つめます。
例えば、
- 「怒られるのが怖い」→ 幼少期に親の怒鳴り声で怯えた記憶
- 「人を助けなきゃ」→ 家庭でケアテイカーとして支え続けた役割
- 「どうせ私はダメ」→ 兄弟内のヒーロー/問題児構造で比較され続けた体験
無意識の正体が見えるほど、あなたを縛っていた鎖は少しずつ解けていきます。
「感じる」練習:フォーカシング
自分軸を取り戻すリハビリとして、まずは感情に気づく練習を。
心理学ではフォーカシングと呼ばれます。
- 今、心にどんな感情がある?
- その感情は身体のどこにある?(胸・喉・お腹など)
- 感情に名前をつける(悲しい/悔しい/寂しい/怒っている)
どんな感情も否定せず、「感じ切る」ことがスタートラインです。
カウンセリングでできること
アダルトチルドレンのカウンセリングでは、
過去の傷を癒すセラピーと現在の思考を整える認知行動療法を併用します。
- 安全にトラウマ記憶を扱い、感情を表現できる場をつくる
- 自己否定のパターンを整理し、自己理解と自己受容を育てる
- 対人関係の癖(迎合・過剰な配慮・境界線の曖昧さ)を見直す
専門家の支援のもとで、
「自分を責める」癖は「自分を信じる」力へと変化していきます。
「自分軸」を育てる3つのステップ
- 自分の感情に正直になる:
「嫌だ」「悲しい」を感じてもいいと自分に許可する。 - 他人と自分の境界線を学ぶ:
相手の気持ちと自分の責任を切り離す練習をする。 - 小さな選択を積み重ねる:
ランチを決める、服を選ぶ等、日常で「自分で決めた」を増やす。
これらは、本来の自分と再会するための現実的なプロセスです。
まとめ
- アダルトチルドレンは機能不全家族で生き延びるために他人軸を学んだ
- 回復の鍵は無意識のパターンに気づくこと
- カウンセリングや心理療法で本来の自分を取り戻せる
- 自分軸は「感情を感じる」「境界線を知る」「選択を重ねる」で育つ
内部リンク(差し替え推奨)
「自分軸を取り戻したい」と感じたら、まずは一歩。安心して話せる場で、一緒に整えていきましょう。